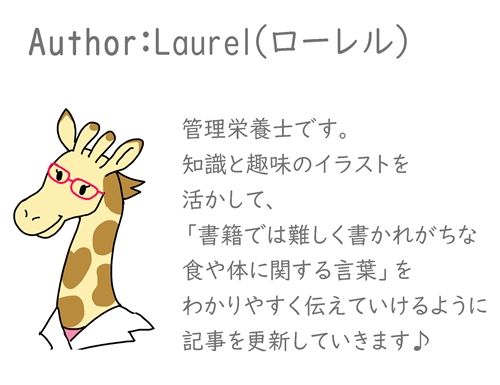【初心者向け】水分活性とは?わかりやすく説明します!
教科書の水分活性の説明ってわかりにくいですよね。
でもここで解決しますよ😊

水分活性とは簡単に言うと、「食品の腐りやすさの指標」のことです!
「Aw(Water Activity)」と呼ばれることもあります。Waterは「水」、Activityは「活発な」という意味です。
残した食べ物をずっとテーブルの上に放置しておくと、腐りますよね。
では、なぜ食べ物は腐るのでしょう?
答えは、細菌やカビなどの微生物がその食べ物を食べ、増えるからです。
微生物が増えるためには、必要なものがあります。
それは、栄養、適度な温度、そして自由水です。
食べ物には二種類の水分が含まれています。
1つは「自由水」、もう1つは「結合水」です。
自由水とは、放置しておけば蒸発したり、微生物が自由に利用できる水のことを言います。
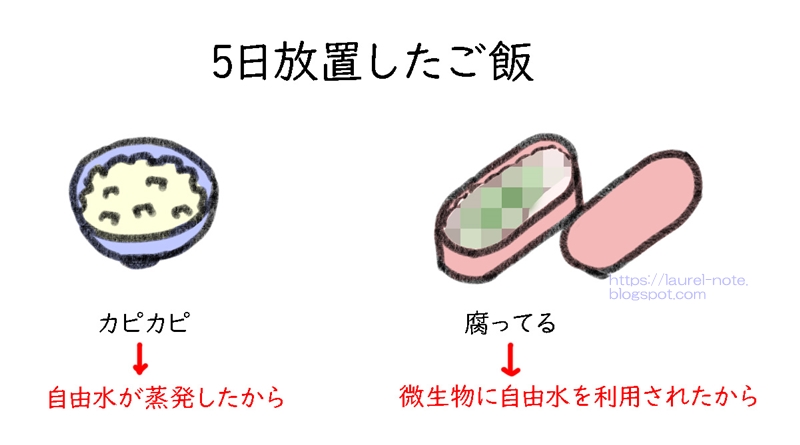
冬、乾燥している部屋にご飯をしばらく置いておけば、ご飯がカピカピになります。これは自由水が蒸発したからです。
夏、湿度の高いお弁当箱の中にご飯を入れっぱなしにしておけば、腐ります。これは微生物に自由水を利用されたからです。
結合水とは、食べ物の成分と完全に結合していて、蒸発もしなければ微生物も利用できない水分のことです。

まだ炊いていない、乾燥した生米にも水分が含まれています。この水分のほとんどは結合水です。
結合水は、お米の成分に完全に結合しているので微生物は利用できません。
水分活性は、食品に含まれる自由水の割合から求めることができます。
食品中の水分の中で、自由水の割合が100%であれば、水分活性は「1」です。
自由水がなければ、水分活性は「0」です。
水分活性「1」…純水
水分活性「0.98~0.99」…炊いたご飯、野菜、果物、生肉、生魚、牛乳
水分活性「0.93~0.97」…パン、ソーセージ
水分活性「0.60~0.85」…米や小麦粉などの乾燥穀物、ナッツ類
水分活性「0.60以下」…飴、乾麺、スキムミルク、コーンフレーク、ビスケット、はちみつなど
水分活性が0.600を下回ると微生物は増殖できなくなります。
水分自体が少なければ、自由水の量も少なくなるので、水分活性が低くなり、食品は腐りにくくなります。

塩分と糖分は、水分と結合します。そのため、塩分・糖分が増えればたくさんの水分が結合するため、自由水が減って結合水が増えます。
例えば梅干しは、水っぽいですが腐りにくい食品です。それは水分が塩分と結合していて、自由水の量が少ないためです。

ここまでの説明を読めばわかると思いますが、
①食品を乾燥させる
②塩分や糖分と水分を結合させる
ことです!
この質問、管理栄養士の国家試験に出題されたことがあるんですよね。
でも、結合水と自由水の関係を理解していれば、楽勝ですね⁈
質問の答えはNO!だって、梅干しみたいに水分が多くても自由水が多いとは限りませんから😁
脂質の酸化は、水分活性が0.3~0.4付近で最も抑制されます。
ビスケットの水分活性は0.33前後なので、ケーキより酸化しにくくなります。
ただし、水分活性が0.3より小さくなっても今度は逆に酸化されやすくなるので、注意が必要です。
でもここで解決しますよ😊
🔶水分活性

水分活性とは?
水分活性とは簡単に言うと、「食品の腐りやすさの指標」のことです!
「Aw(Water Activity)」と呼ばれることもあります。Waterは「水」、Activityは「活発な」という意味です。
食べ物が腐る原因
残した食べ物をずっとテーブルの上に放置しておくと、腐りますよね。
では、なぜ食べ物は腐るのでしょう?
答えは、細菌やカビなどの微生物がその食べ物を食べ、増えるからです。
微生物が増えるためには、必要なものがあります。
それは、栄養、適度な温度、そして自由水です。
自由水とは?
食べ物には二種類の水分が含まれています。
1つは「自由水」、もう1つは「結合水」です。
自由水とは、放置しておけば蒸発したり、微生物が自由に利用できる水のことを言います。
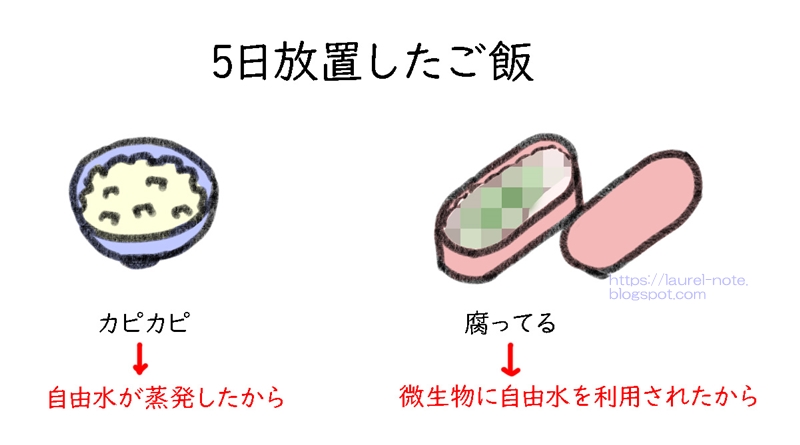
冬、乾燥している部屋にご飯をしばらく置いておけば、ご飯がカピカピになります。これは自由水が蒸発したからです。
夏、湿度の高いお弁当箱の中にご飯を入れっぱなしにしておけば、腐ります。これは微生物に自由水を利用されたからです。
結合水とは?
結合水とは、食べ物の成分と完全に結合していて、蒸発もしなければ微生物も利用できない水分のことです。

まだ炊いていない、乾燥した生米にも水分が含まれています。この水分のほとんどは結合水です。
結合水は、お米の成分に完全に結合しているので微生物は利用できません。
それを数値化するのが「水分活性」
水分活性は、食品に含まれる自由水の割合から求めることができます。
食品中の水分の中で、自由水の割合が100%であれば、水分活性は「1」です。
自由水がなければ、水分活性は「0」です。
水分活性が高い代表的なもの
水分活性「1」…純水
水分活性「0.98~0.99」…炊いたご飯、野菜、果物、生肉、生魚、牛乳
水分活性「0.93~0.97」…パン、ソーセージ
水分活性が低い代表的なもの
水分活性「0.60~0.85」…米や小麦粉などの乾燥穀物、ナッツ類
水分活性「0.60以下」…飴、乾麺、スキムミルク、コーンフレーク、ビスケット、はちみつなど
水分活性が0.600を下回ると微生物は増殖できなくなります。
水分活性が低くなる条件
乾燥
水分自体が少なければ、自由水の量も少なくなるので、水分活性が低くなり、食品は腐りにくくなります。

塩分・糖分
塩分と糖分は、水分と結合します。そのため、塩分・糖分が増えればたくさんの水分が結合するため、自由水が減って結合水が増えます。
例えば梅干しは、水っぽいですが腐りにくい食品です。それは水分が塩分と結合していて、自由水の量が少ないためです。

水分活性を下げる方法
ここまでの説明を読めばわかると思いますが、
①食品を乾燥させる
②塩分や糖分と水分を結合させる
ことです!
水分活性と水分含量は比例するの?
この質問、管理栄養士の国家試験に出題されたことがあるんですよね。
でも、結合水と自由水の関係を理解していれば、楽勝ですね⁈
質問の答えはNO!だって、梅干しみたいに水分が多くても自由水が多いとは限りませんから😁
脂質の酸化との関係
脂質の酸化は、水分活性が0.3~0.4付近で最も抑制されます。
ビスケットの水分活性は0.33前後なので、ケーキより酸化しにくくなります。
ただし、水分活性が0.3より小さくなっても今度は逆に酸化されやすくなるので、注意が必要です。