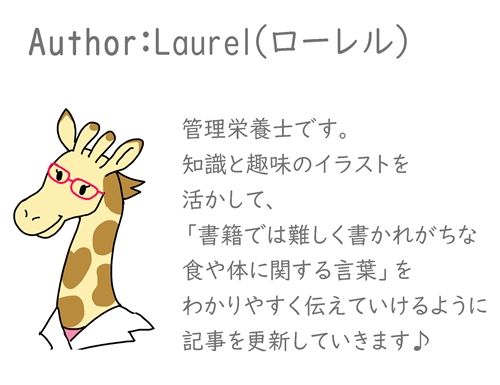魚の放射能の今は?他にも危険な物質はある?食べすぎると体に蓄積される恐怖の毒素-魚介類を食べるうえででの注意点ついて
魚って本当に安全なの?とたまに聞かれるので、今回は魚の危険性についての特集です!

魚 魚 魚~♪魚~を~食べ~ると~♪
頭 頭 頭~♪頭~が~良く~なる~♪
なんて歌が昔流行りましたよね。
そう。
お魚にはDHAがたっぷり含まれていて、記憶力の助けをしてくれます。
また、EPAという物質も含まれていて、この栄養素は血液をサラサラにし、動脈硬化を予防してくれます。
更に、DHAやEPAは、うつ病などの精神疾患を予防してくれるとも言われています。
大切な脂肪酸だけではなく、魚に含まれるたんぱく質はアミノ酸スコアが100なので、「良質なたんぱく質」といわれ、
お肌の細胞を作ってくれたり、髪の毛や爪をキレイにしてくれたり、筋トレの後には新しい筋肉を作ってくれたりします。
小魚を骨ごと食べればカルシウムも豊富で骨粗しょう症の予防にもなります。

なーんて、思ってはいけません。
この世には、「これさえ食べれば健康でいられる」という食べ物はなく、良い部分があれば、もちろん悪い部分もあります。
たとえば、魚には汚染された海のゴミが蓄積されていたりします。
そのゴミはどんなものがあるのか、
たくさん食べると、どんな悪いことが起こるか…
確認してみましょう。
ダイオキシン

①PCDD→ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン
②PCDF→ポリ塩化ジペンゾフラン
③PCB(コプラナ)→コプラナーポリ塩化ビフェニル
これらを合わせてダイオキシンと呼んでいます。
ダイオキシンは、燃やせないゴミが燃やされた時に発生したり、タバコの煙や排気ガスから発生する有害物質です。
発ガン性や催奇形性があり、また生殖機能、甲状腺機能、免疫機能を悪くさせます。
油に溶けやすい性質のため、人の体の中に入ると脂肪組織に残留しやすいと言われています。
一度体の中に入ると、体内のダイオキシンが半分の量になるまで約7年かかります。
体内に蓄積されたダイオキシンは、母乳の中に入り込むことがあります。
人間の脂肪に残留すると説明しましたが、同じように動物の脂肪にも残留しやすいため、魚介類の体にも残留します。
燃やしてはいけないゴミを燃やして発生した煙を牛や豚が吸って、家畜にダイオキシンが蓄積する場合もあります。
日本では燃やせないごみの分別に力を入れてからはダイオキシンの排出が少なくなりました。
しかし、少なくなっただけで毎日どこかで燃やせないごみは燃やされています。
またタバコからのダイオキシンも出ています。
排ガスも出ています。
更に、大気汚染について力を入れていない発展途上国ではダイオキシンが出続けています。
最近はあまり騒がれなくなりましたが、毎日ダイオキシンは出ているのは事実なので、魚が持っていてもおかしくありません。

昭和31年に熊本県水俣市のチッソ水俣工場が、工業排水を水俣湾に排出していたことで、その工業用水を体内にとりいれた魚を食べて多くの方が亡くなったという悲しいニュースがありました。
この工業用水にはメチル水銀が入っており、それが食物連鎖の末に凝縮され、それを食べた人に害を及ぼしました。
それ以降は日本では水銀を海に流すことはなくなりましたが、水銀を排出している国はあります。
そのため、マグロや金目鯛など、広い海を回遊する肉食の魚にはメチル水銀が濃縮されている可能性があります。
水銀は脂溶性で、中枢神経に移行しやすいと言われています。
また、妊婦さんが水銀を多く摂取した場合、胎盤を経由するので、障害を持つ子どもがが生まれる可能性があります。

2011年3月11日に東日本大震災で、福島第一原子力発電所の原子炉がメルトダウンを起こし、大量の放射性物質が漏洩してしまいました。
その放射性物質はいくつか種類があります。

セシウム134の物理学的半減期は約2年と言われています。
つまり、セシウム134が海に流れ出てから、その半分が別の元素に変わるまで2年かかる、という意味です。
2018年現在、自信から7年経過しているので、おそらくセシウム134はほぼなくなっているでしょう。
しかし問題はセシウム137です。
なんとセシウム137の物理的半減期は約30年もあります。
つまり、セシウム137が海に流れ出てから、その半分が別の元素に変わるまで30年かかる、ということになります。
ということは、海にはセシウム137が今もなお存在しています。
海はかなり広いので濃度は低いのでしょうが、やはりそれを体内にとりいれる魚はいます。
そして回遊して日本のさまざまな場所(東北以外)で水揚げされるのも事実です。
〇〇産と書いてある魚は、水揚げされた場所を指します。
セシウムはナトリウムやカリウムと似たような働きをするので、海の水に良く溶け、生物の体に容易に入ってきます。
セシウム137は、人の体内に入ると全身の筋肉組織に集積し、特に生殖腺などに障害を起こします。
なのでセシウム137が多く含まれる魚介類を食べるのは危険です。
しかし一般にスーパーなどで出回っている魚介類は放射能の検査を行っているみたいなので食べても大丈夫とのことです。(実際に測定しているところを見たわけではないので確信はないですが)

実はストロンチウム90の物理学的半減期も30年です。
ストロンチウムはカルシウムに似た性質をもっており、体内に入ると骨の中のカルシウムと置き換わります。
一度骨の中に入ると、放射線を出し続けるため大変危険なものです。骨髄の造血機能障害が起こる可能性もあります。
ただし、揮発性化合物を作りにくいので原発事故で放出された量はセシウム137よりもずっと少ないそうです。

コバルトの物理学的半減期は5年です。
海の中のコバルトが半分になるのに5年かかるということですから、
完全になくなるまで10年はかかるのでまだ海に存在します。
体内の蓄積されると、肝臓や、卵巣に障害を起こすと言われています。

プルトニウムは、体内に入れてもほぼ蓄積はされませんが、一部は肝臓や骨に蓄積して長期間残留する場合もあるようです。
物理学的半減期は、細かい種類によって異なりますが、短い物で5時間、長い物でなんと約8000万年もかかるそうです。
【ちなみに】
・ヨウ素131という物質は、物理学的半減期は約8日と短いので、現在はほとんど検出することがなくなったようです。
・トリチウムという物質は、体に取り込まれても蓄積されません。
平成24年4月に放射線物質の基準値が定められました。
基準値を超えた食品は、出荷ができないことになっています。
・飲料水…10Bq/kg
・牛乳…50Bq/kg
・乳児用食品…50Bq/kg
・一般食品…100Bq/kg
例えば一般食品の場合、1kgあたり100Bq(100ベクレル)の放射性物質を検出したらアウト、ということです。
放射性物質を含んだ食品は、加熱したり冷凍したりしてもなくなりません。
国は魚を食べることを「問題ない」としていますが、放射性物質は目に見えないので怖いですよね。
市場に出回っているものを適量食べるだけなら大丈夫だとは思いますが、
あまり食べすぎたり、誰かが釣ってきたものを気軽に食べないようにしたいところです。

最近メディアや雑誌でよく取り上げられていますよね。
人間が利便性のために作ったプラスチック。
容器や食品の袋など、さまざまなところで使われています。
このゴミが海に捨てられ、それが風化し、粉々になったものがマイクロプラスチックです。
大きさが5ミリ以下、つまり砂くらいの小さいサイズになり、海の中を漂うので、魚が餌と間違えて食べてしまいます。
プラスチックにより満腹になった魚は、他の餌を食べられなくなって栄養失調になってしまったり、
石油から溶け出しているプラスチックは、油に溶けやすい有害な化学物質が付きやすい性質をもっているそうです。
具体的な化学物質の情報はありませんでしたが、油に溶けやすい化学物質といえば、ダイオキシンでしょうか。
その有害な化学物質が付いているマイクロプラスチックを食べた小魚がさらに大きな魚に食べられ…と食物連鎖が起こり、生態系に影響が及ぼすことも。
さらに、有害な化学物質が付いたマイクロプラスチックを食べた魚を人間が食べると、化学物質が高濃度の場合、発がん性や免疫機能に影響を及ぼすとか。
今の段階では、高濃度に化学物質がついているプラスチックを食べた魚はいないらしいので、専門家の先生は大丈夫と言っているようです。
もちろんマイクロプラスチックだけではなく、普通のプラスチック…例えばお菓子の包み紙や生活用品のゴミなどを魚が丸呑みして消化できずにいる、ということもよくあることなので、プラスチックごみについては今後考えていかなくてはいけない問題だと思います。
色々とみてきたら何となく魚が怖くなってきますが、
適量食べるのなら全く問題ありません。
1日60g程度が目安です。
鮭、まぐろ、カツオ、さば、さんま、タラ、ししゃもなど、
スーパーで売っているような魚なら、どんな魚でもOKです。
60gとは、だいたいツナ缶1つ分くらいです。
少なく感じますか?
もしガッツリ食べたければ、
2日に1回120gという感じでも大丈夫です。
一週間トータルで見て、だいたい1日60gくらい魚を食べられていれば、問題ありません。
ただし、すじこやタラコ、イカの塩辛、佃煮など、それだけで食べるとかなりしょっぱい味付けの魚介類は、塩分のとりすぎになるので60gも食べてはいけません。
α-リノレン酸の含まれている、「アマニ油」「エゴマ油」「シソ油」を毎日ティースプーン1杯分ほど摂取することをお勧めします。
上記の3つならどれでもかまいません。
α-リノレン酸は、必須脂肪酸であり、体内でDHAやEPAに変換されることがわかっています。
なので、魚のアレルギーなどで食べられなくても問題ありません。
🔶海洋汚染

魚 魚 魚~♪魚~を~食べ~ると~♪
頭 頭 頭~♪頭~が~良く~なる~♪
なんて歌が昔流行りましたよね。
そう。
お魚にはDHAがたっぷり含まれていて、記憶力の助けをしてくれます。
また、EPAという物質も含まれていて、この栄養素は血液をサラサラにし、動脈硬化を予防してくれます。
更に、DHAやEPAは、うつ病などの精神疾患を予防してくれるとも言われています。
大切な脂肪酸だけではなく、魚に含まれるたんぱく質はアミノ酸スコアが100なので、「良質なたんぱく質」といわれ、
お肌の細胞を作ってくれたり、髪の毛や爪をキレイにしてくれたり、筋トレの後には新しい筋肉を作ってくれたりします。
小魚を骨ごと食べればカルシウムも豊富で骨粗しょう症の予防にもなります。

魚ってそんなに体にいいんだ!
それなら毎日、たくさん食べよう!!
最近、糖質制限ダイエットも流行ってるし、もうこの際ご飯はいらない!
野菜もいらないでしょ?!
魚さえ食べてれば健康でいられるでしょ♪
それなら毎日、たくさん食べよう!!
最近、糖質制限ダイエットも流行ってるし、もうこの際ご飯はいらない!
野菜もいらないでしょ?!
魚さえ食べてれば健康でいられるでしょ♪
なーんて、思ってはいけません。
この世には、「これさえ食べれば健康でいられる」という食べ物はなく、良い部分があれば、もちろん悪い部分もあります。
たとえば、魚には汚染された海のゴミが蓄積されていたりします。
そのゴミはどんなものがあるのか、
たくさん食べると、どんな悪いことが起こるか…
確認してみましょう。
もくじ
・ダイオキシン
・メチル水銀
・放射性物質
セシウム134,137
ストロンチウム90
コバルト
プルトニウム
食品中の放射性物質の基準値
・マイクロプラスチック
・適量とは?食べる頻度の目安
・魚が苦手な人は
・まとめ
・ダイオキシン
・メチル水銀
・放射性物質
セシウム134,137
ストロンチウム90
コバルト
プルトニウム
食品中の放射性物質の基準値
・マイクロプラスチック
・適量とは?食べる頻度の目安
・魚が苦手な人は
・まとめ
~魚に含まれる怖い物質~
ダイオキシン

①PCDD→ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン
②PCDF→ポリ塩化ジペンゾフラン
③PCB(コプラナ)→コプラナーポリ塩化ビフェニル
これらを合わせてダイオキシンと呼んでいます。
ダイオキシンは、燃やせないゴミが燃やされた時に発生したり、タバコの煙や排気ガスから発生する有害物質です。
発ガン性や催奇形性があり、また生殖機能、甲状腺機能、免疫機能を悪くさせます。
油に溶けやすい性質のため、人の体の中に入ると脂肪組織に残留しやすいと言われています。
一度体の中に入ると、体内のダイオキシンが半分の量になるまで約7年かかります。
体内に蓄積されたダイオキシンは、母乳の中に入り込むことがあります。
人間の脂肪に残留すると説明しましたが、同じように動物の脂肪にも残留しやすいため、魚介類の体にも残留します。
燃やしてはいけないゴミを燃やして発生した煙を牛や豚が吸って、家畜にダイオキシンが蓄積する場合もあります。
日本では燃やせないごみの分別に力を入れてからはダイオキシンの排出が少なくなりました。
しかし、少なくなっただけで毎日どこかで燃やせないごみは燃やされています。
またタバコからのダイオキシンも出ています。
排ガスも出ています。
更に、大気汚染について力を入れていない発展途上国ではダイオキシンが出続けています。
最近はあまり騒がれなくなりましたが、毎日ダイオキシンは出ているのは事実なので、魚が持っていてもおかしくありません。
メチル水銀

昭和31年に熊本県水俣市のチッソ水俣工場が、工業排水を水俣湾に排出していたことで、その工業用水を体内にとりいれた魚を食べて多くの方が亡くなったという悲しいニュースがありました。
この工業用水にはメチル水銀が入っており、それが食物連鎖の末に凝縮され、それを食べた人に害を及ぼしました。
それ以降は日本では水銀を海に流すことはなくなりましたが、水銀を排出している国はあります。
そのため、マグロや金目鯛など、広い海を回遊する肉食の魚にはメチル水銀が濃縮されている可能性があります。
水銀は脂溶性で、中枢神経に移行しやすいと言われています。
また、妊婦さんが水銀を多く摂取した場合、胎盤を経由するので、障害を持つ子どもがが生まれる可能性があります。
放射性物質

2011年3月11日に東日本大震災で、福島第一原子力発電所の原子炉がメルトダウンを起こし、大量の放射性物質が漏洩してしまいました。
その放射性物質はいくつか種類があります。
セシウム134,137

セシウム134の物理学的半減期は約2年と言われています。
つまり、セシウム134が海に流れ出てから、その半分が別の元素に変わるまで2年かかる、という意味です。
2018年現在、自信から7年経過しているので、おそらくセシウム134はほぼなくなっているでしょう。
しかし問題はセシウム137です。
なんとセシウム137の物理的半減期は約30年もあります。
つまり、セシウム137が海に流れ出てから、その半分が別の元素に変わるまで30年かかる、ということになります。
ということは、海にはセシウム137が今もなお存在しています。
海はかなり広いので濃度は低いのでしょうが、やはりそれを体内にとりいれる魚はいます。
そして回遊して日本のさまざまな場所(東北以外)で水揚げされるのも事実です。
〇〇産と書いてある魚は、水揚げされた場所を指します。
セシウムはナトリウムやカリウムと似たような働きをするので、海の水に良く溶け、生物の体に容易に入ってきます。
セシウム137は、人の体内に入ると全身の筋肉組織に集積し、特に生殖腺などに障害を起こします。
なのでセシウム137が多く含まれる魚介類を食べるのは危険です。
しかし一般にスーパーなどで出回っている魚介類は放射能の検査を行っているみたいなので食べても大丈夫とのことです。(実際に測定しているところを見たわけではないので確信はないですが)
ストロンチウム90

実はストロンチウム90の物理学的半減期も30年です。
ストロンチウムはカルシウムに似た性質をもっており、体内に入ると骨の中のカルシウムと置き換わります。
一度骨の中に入ると、放射線を出し続けるため大変危険なものです。骨髄の造血機能障害が起こる可能性もあります。
ただし、揮発性化合物を作りにくいので原発事故で放出された量はセシウム137よりもずっと少ないそうです。
コバルト

コバルトの物理学的半減期は5年です。
海の中のコバルトが半分になるのに5年かかるということですから、
完全になくなるまで10年はかかるのでまだ海に存在します。
体内の蓄積されると、肝臓や、卵巣に障害を起こすと言われています。
プルトニウム

プルトニウムは、体内に入れてもほぼ蓄積はされませんが、一部は肝臓や骨に蓄積して長期間残留する場合もあるようです。
物理学的半減期は、細かい種類によって異なりますが、短い物で5時間、長い物でなんと約8000万年もかかるそうです。
【ちなみに】
・ヨウ素131という物質は、物理学的半減期は約8日と短いので、現在はほとんど検出することがなくなったようです。
・トリチウムという物質は、体に取り込まれても蓄積されません。
食品中の放射性物質の基準値
平成24年4月に放射線物質の基準値が定められました。
基準値を超えた食品は、出荷ができないことになっています。
・飲料水…10Bq/kg
・牛乳…50Bq/kg
・乳児用食品…50Bq/kg
・一般食品…100Bq/kg
例えば一般食品の場合、1kgあたり100Bq(100ベクレル)の放射性物質を検出したらアウト、ということです。
放射性物質を含んだ食品は、加熱したり冷凍したりしてもなくなりません。
国は魚を食べることを「問題ない」としていますが、放射性物質は目に見えないので怖いですよね。
市場に出回っているものを適量食べるだけなら大丈夫だとは思いますが、
あまり食べすぎたり、誰かが釣ってきたものを気軽に食べないようにしたいところです。
マイクロプラスチック

最近メディアや雑誌でよく取り上げられていますよね。
人間が利便性のために作ったプラスチック。
容器や食品の袋など、さまざまなところで使われています。
このゴミが海に捨てられ、それが風化し、粉々になったものがマイクロプラスチックです。
大きさが5ミリ以下、つまり砂くらいの小さいサイズになり、海の中を漂うので、魚が餌と間違えて食べてしまいます。
プラスチックにより満腹になった魚は、他の餌を食べられなくなって栄養失調になってしまったり、
石油から溶け出しているプラスチックは、油に溶けやすい有害な化学物質が付きやすい性質をもっているそうです。
具体的な化学物質の情報はありませんでしたが、油に溶けやすい化学物質といえば、ダイオキシンでしょうか。
その有害な化学物質が付いているマイクロプラスチックを食べた小魚がさらに大きな魚に食べられ…と食物連鎖が起こり、生態系に影響が及ぼすことも。
さらに、有害な化学物質が付いたマイクロプラスチックを食べた魚を人間が食べると、化学物質が高濃度の場合、発がん性や免疫機能に影響を及ぼすとか。
今の段階では、高濃度に化学物質がついているプラスチックを食べた魚はいないらしいので、専門家の先生は大丈夫と言っているようです。
もちろんマイクロプラスチックだけではなく、普通のプラスチック…例えばお菓子の包み紙や生活用品のゴミなどを魚が丸呑みして消化できずにいる、ということもよくあることなので、プラスチックごみについては今後考えていかなくてはいけない問題だと思います。
色々とみてきたら何となく魚が怖くなってきますが、
適量食べるのなら全く問題ありません。
適量とは?食べる頻度の目安
1日60g程度が目安です。
鮭、まぐろ、カツオ、さば、さんま、タラ、ししゃもなど、
スーパーで売っているような魚なら、どんな魚でもOKです。
60gとは、だいたいツナ缶1つ分くらいです。
少なく感じますか?
もしガッツリ食べたければ、
2日に1回120gという感じでも大丈夫です。
一週間トータルで見て、だいたい1日60gくらい魚を食べられていれば、問題ありません。
ただし、すじこやタラコ、イカの塩辛、佃煮など、それだけで食べるとかなりしょっぱい味付けの魚介類は、塩分のとりすぎになるので60gも食べてはいけません。
魚が苦手な人は
α-リノレン酸の含まれている、「アマニ油」「エゴマ油」「シソ油」を毎日ティースプーン1杯分ほど摂取することをお勧めします。
上記の3つならどれでもかまいません。
α-リノレン酸は、必須脂肪酸であり、体内でDHAやEPAに変換されることがわかっています。
なので、魚のアレルギーなどで食べられなくても問題ありません。
まとめ
このように、人間による環境汚染のせいで、魚にはいろいろな化学物質が蓄積されている場合があります。
人間に必要な分を食べるのであれば、ほぼ問題はありませんが、食べ過ぎてしまうと健康状態が悪くなる恐れがあります。
いくら体にいいと言っても、ほどほどが大事なのです。
このように、人間による環境汚染のせいで、魚にはいろいろな化学物質が蓄積されている場合があります。
人間に必要な分を食べるのであれば、ほぼ問題はありませんが、食べ過ぎてしまうと健康状態が悪くなる恐れがあります。
いくら体にいいと言っても、ほどほどが大事なのです。