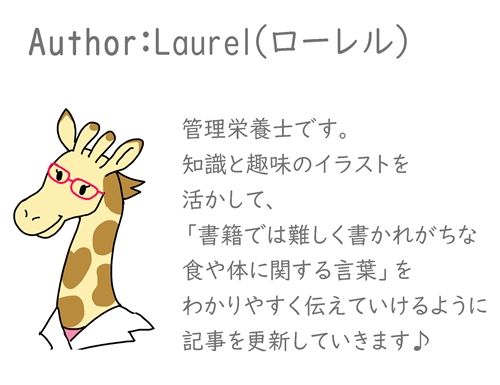【グリア細胞とは?】神経細胞との違いをわかりやすく説明!
グリア細胞と神経細胞って何が違うの?
グリア細胞の種類は?

簡単に言うと、神経細胞をサポートする細胞です。(※神経細胞は情報を伝達する細胞です。詳しくは→【ニューロン・シナプスをわかりやすく説明!】)
例えば、神経細胞の軸索には「シュワン細胞(鞘細胞)」が付いていましたよね。

これも、ニューロンの情報伝達をサポートするものなので、グリア細胞です。
シュワン細胞って何?→【神経に関する用語を説明!】


グリアとは、「glue」つまり「膠(にかわ)」のこと。
膠とは、ゼラチンと同じ材料(動物のコラーゲン)で作られた接着剤です。
工芸品などに使われます。
そのため、日本名では「神経膠細胞(しんけいこうさいぼう)」と呼ばれます。
主に神経細胞の構造の支持や、栄養分の補給をしています。
教科書でよくピックアップされる、代表的なグリア細胞を4つご紹介しますね😉
アストログリア

発見当初、星(アストロ:astro)のような形をしていたのでこう名付けられました。
【主な働き】
神経細胞の支え、栄養を供給


オリゴデンドログリア

「オリゴ:oligo」は少ない、「デンドロ:dendro」は突起のこと。※ちなみに「サイト:cyte」は細胞。
アストログリアよりも細胞から出る突起が少ないため、こう名付けられました。
【主な働き】
中枢神経の軸索の髄鞘を形成して、情報伝達の速度を上げます。
◆オリゴデンドログリアとシュワン細胞の違い
つまり、
・中枢神経(脳と脊髄)で髄鞘を形成するのは、オリゴデンドログリア。
・末梢神経(脳と脊髄以外)で髄鞘を形成するシュワン細胞。
・二つは同じ働きをするグリア細胞。
・オリゴデンドログリアは突起があり、シュワン細胞は突起がない。
ということになります。
※シュワン細胞の突起が軸索に巻き付いて髄鞘を形成していると説明する文献もあります。



「ミクロ:micro」は極小という意味です。
名前の通り、他と比べて小さいグリア細胞です。
【主な働き】
壊れたニューロンを回収するなど、免疫に関与しています。
【元ネタ】
スパイダー(手塚治虫先生キャラ)

【主な働き】
脳室の壁を構成しています。
壁を構成していて上着のような存在なので、上衣細胞と名付けられました。
【元ネタ】
ヒョウタンツギ(手塚治虫先生のキャラ)

・神経細胞は、主に情報を伝達するための細胞の総称。
・グリア細胞は、主に神経細胞をサポートする細胞。
・教科書でよく紹介されるのは、「アストログリア」「オリゴデンドログリア」「ミクログリア」「上衣細胞」
・末梢神経のニューロンの軸索についている「シュワン細胞」もグリア細胞。
今回は私が最も尊敬するマンガ家、手塚治虫氏のキャラクターをグリア細胞に当てはめてみました。(体の形がキモくなってゴメンナサイ。)
知っているキャラが難しい単語に当てはまると、何となくイメージして覚えられるもんです。
え?ウランちゃん、ヒョウタンツギ、スパイダーを知らないって?(さすがにアトムは知っているよね?)
手塚作品によく出てくるキャラなのでこの際覚えちゃってくださいね😁
【オススメ作品】
⭐ブラックジャック:医学を学べるのはもちろん、1話完結の中で繰り広げられる、心温まる人間模様が毎回胸を打たれます。
⭐火の鳥:絵は可愛らしいですが、「なんで自分は生きているんだろう?」「生きるってなんだろう?」と哲学を考えさせられます。
⭐夜の声(「空気の底」の中の短編):「世にも奇妙な物語」として映像化されました。大切なものはお金なのか、それとも最も心を許せる人なのかを考えさせられる一作。普通の恋愛物ではなく、歯がゆさが残るバッドエンド。
約50年も前に描かれた漫画なのに、今見ても感動できるのって本当にすごいです。
↓Kindle版(電子書籍)
関連記事はコチラ
➜ サイトのもくじ【体の構造】
グリア細胞の種類は?
🔶グリア細胞

グリア細胞とは?
簡単に言うと、神経細胞をサポートする細胞です。(※神経細胞は情報を伝達する細胞です。詳しくは→【ニューロン・シナプスをわかりやすく説明!】)
例えば、神経細胞の軸索には「シュワン細胞(鞘細胞)」が付いていましたよね。

これも、ニューロンの情報伝達をサポートするものなので、グリア細胞です。
シュワン細胞って何?→【神経に関する用語を説明!】
「グリア」とは?

グリアとは、「glue」つまり「膠(にかわ)」のこと。
膠とは、ゼラチンと同じ材料(動物のコラーゲン)で作られた接着剤です。
工芸品などに使われます。
そのため、日本名では「神経膠細胞(しんけいこうさいぼう)」と呼ばれます。
サポートの内容は?
主に神経細胞の構造の支持や、栄養分の補給をしています。
代表的なグリア細胞
教科書でよくピックアップされる、代表的なグリア細胞を4つご紹介しますね😉
アストログリア
(別名:アストロサイト、星状神経膠細胞)

発見当初、星(アストロ:astro)のような形をしていたのでこう名付けられました。
【主な働き】
神経細胞の支え、栄養を供給

「グリア細胞の働き」として紹介される事柄は、アストロサイトの働きのケースがほとんどです!(画像:アストロボーイ・鉄腕アトムより)
オリゴデンドログリア
(別名:オリゴデンドロサイト、希突起神経膠細胞、稀突起膠細胞)

「オリゴ:oligo」は少ない、「デンドロ:dendro」は突起のこと。※ちなみに「サイト:cyte」は細胞。
アストログリアよりも細胞から出る突起が少ないため、こう名付けられました。
【主な働き】
中枢神経の軸索の髄鞘を形成して、情報伝達の速度を上げます。
◆オリゴデンドログリアとシュワン細胞の違い
脳とグリア細胞-見えてきた!脳機能のカギを握る細胞たち- P75から引用
P75から引用
「(前略)末梢のシュワン細胞と呼ばれる細胞には突起がありません。そのため、突起がないグリア細胞という意味で、日本語には「乏突起膠細胞」と訳されることもあります。けれど、その役割も細胞の性質もオリゴデンドログリアと同じです。」
↑著者がグリア細胞にインタビューしていて面白い本です。
「(前略)末梢のシュワン細胞と呼ばれる細胞には突起がありません。そのため、突起がないグリア細胞という意味で、日本語には「乏突起膠細胞」と訳されることもあります。けれど、その役割も細胞の性質もオリゴデンドログリアと同じです。」
↑著者がグリア細胞にインタビューしていて面白い本です。
つまり、
・中枢神経(脳と脊髄)で髄鞘を形成するのは、オリゴデンドログリア。
・末梢神経(脳と脊髄以外)で髄鞘を形成するシュワン細胞。
・二つは同じ働きをするグリア細胞。
・オリゴデンドログリアは突起があり、シュワン細胞は突起がない。
ということになります。
※シュワン細胞の突起が軸索に巻き付いて髄鞘を形成していると説明する文献もあります。

「主なグリア細胞」としてシュワン細胞が紹介されていない教科書が多いのが不思議なのよね。
ミクログリア

「ミクロ:micro」は極小という意味です。
名前の通り、他と比べて小さいグリア細胞です。
【主な働き】
壊れたニューロンを回収するなど、免疫に関与しています。
【元ネタ】
スパイダー(手塚治虫先生キャラ)
上衣細胞

【主な働き】
脳室の壁を構成しています。
壁を構成していて上着のような存在なので、上衣細胞と名付けられました。
【元ネタ】
ヒョウタンツギ(手塚治虫先生のキャラ)
まとめ

・神経細胞は、主に情報を伝達するための細胞の総称。
・グリア細胞は、主に神経細胞をサポートする細胞。
・教科書でよく紹介されるのは、「アストログリア」「オリゴデンドログリア」「ミクログリア」「上衣細胞」
・末梢神経のニューロンの軸索についている「シュワン細胞」もグリア細胞。
今回は私が最も尊敬するマンガ家、手塚治虫氏のキャラクターをグリア細胞に当てはめてみました。(体の形がキモくなってゴメンナサイ。)
知っているキャラが難しい単語に当てはまると、何となくイメージして覚えられるもんです。
え?ウランちゃん、ヒョウタンツギ、スパイダーを知らないって?(さすがにアトムは知っているよね?)
手塚作品によく出てくるキャラなのでこの際覚えちゃってくださいね😁
【オススメ作品】
⭐ブラックジャック:医学を学べるのはもちろん、1話完結の中で繰り広げられる、心温まる人間模様が毎回胸を打たれます。
⭐火の鳥:絵は可愛らしいですが、「なんで自分は生きているんだろう?」「生きるってなんだろう?」と哲学を考えさせられます。
⭐夜の声(「空気の底」の中の短編):「世にも奇妙な物語」として映像化されました。大切なものはお金なのか、それとも最も心を許せる人なのかを考えさせられる一作。普通の恋愛物ではなく、歯がゆさが残るバッドエンド。
約50年も前に描かれた漫画なのに、今見ても感動できるのって本当にすごいです。
↓Kindle版(電子書籍)
関連記事はコチラ
➜ サイトのもくじ【体の構造】